![]() 「眼鏡橋」のおはなしvol.1
「眼鏡橋」のおはなしvol.1
訪れる前にチェックしたい! 眼鏡橋“キホン”のおはなし。

眼鏡橋は、長崎市の中心部を通り抜ける中島川に架かる、長崎を代表するおなじみの観光スポットです。長さ22m、幅は3.65m、川面までの高さ5.46mの日本初の石造りアーチ橋。
「日本橋」や「錦帯橋」と並んで“日本三名橋”にも挙げられています。
寛永11(1634)年、興福寺二代目住職の黙子如定(もくすにょじょう)が、中国から石工を呼び寄せて眼鏡橋を建造したとされています。
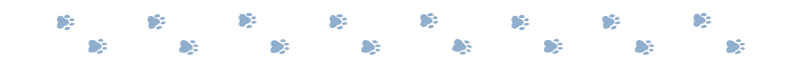
名前の由来は、橋と、その川面に映った影が二つの円を描き“メガネ”に見えることから。
1960年(昭和35年)に国の重要文化財に指定されました。1982年(昭和57年)の長崎大水害の際に一部損壊してしまいますが、現在は修復されて、観光はもちろん地元住民の生活の一部にもなっています。

中国から渡来してきた高僧。眼鏡橋のほか、中国のさまざまな先進技術を導入したと言われています。もともとは、興福寺の参詣者のために架けられた橋であったようです。
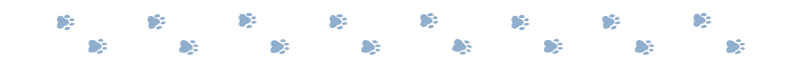
遊歩道の下に水路が!
長崎大水害の後、眼鏡橋の両岸には、防災のためにバイパス水路が造られました。

常磐橋からは、左右の遊歩道の下に水路が造られているのを見ることができます。川の氾濫を防ぐために、魚市橋あたりから常磐橋の手前まで、水量が多い時の水の逃げ道を造っているんです。災害対策をしながらも、川幅を広げることなく橋をそのままの形で保つ。雨のまち、そして観光都市・長崎ならではの工夫ですね。

バイパス水路は、諏訪町のある東側(中通り側) と魚の町の西側(電車通り・市民会館側)に分かれています。その上にある遊歩道が幅広なのに合わせて、西側の方が幅が広く取られています。東新橋はほかの橋と比べて背が高いので、見晴らし抜群でチェックすることができますよ。
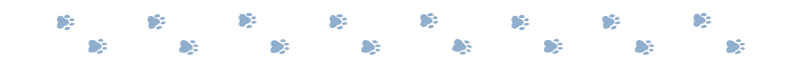

バイパス水路の上にできた道幅は遊歩道として活かされ、今では毎日のように観光客が訪れ、地元の人たちの憩いの場となっています。
AD注目の実力店や伝統の味を守り続ける老舗店など、全900軒が掲載!長崎の新店・定番店など美味しいお店が勢揃い。県内全域を網羅したグルメガイド本、書店にて絶賛発売中!
| 名称 | 眼鏡橋 |
|---|---|
| アクセス | 【JR長崎駅から】路面電車3号系統「蛍茶屋 行き」に乗車→「市民会館」電停下車→徒歩4分 【大浦天主堂・中華街方面から】路面電車4号系統・5号系統「蛍茶屋 行き」に乗車→「眼鏡橋」電停下車→徒歩3分 |
| 駐車場 | 周辺にコインパーキングあり |
| 備考 | 国指定重要文化財(指定年月日 昭和35年2月9日) |
| 場所 | 長崎県長崎市 魚の町・栄町と諏訪町・古川町の間 |
眼鏡橋の他のお話はこちら
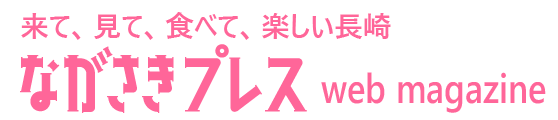


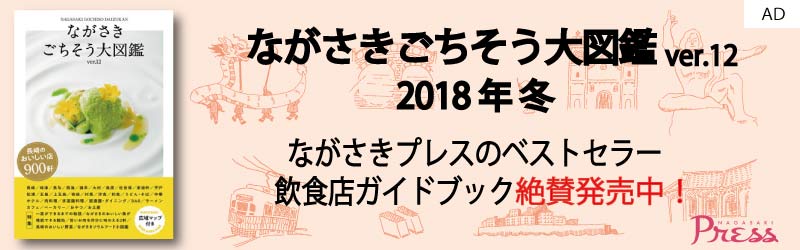

コメントを投稿するにはログインしてください。