![]() 「眼鏡橋」のおはなしvol.2
「眼鏡橋」のおはなしvol.2
修学旅行で自慢できる!眼鏡橋“もう一歩”踏み込んだおはなし。

実は、この中島川に架かる橋は、眼鏡橋だけではありません。「中島川石造アーチ橋群」と呼ばれ、現在もたくさんの石橋が残っています。

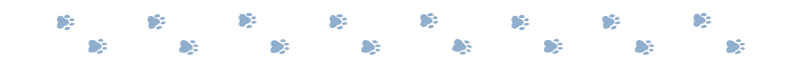
前回の「眼鏡橋vol.1“キホン”のおはなし」でも触れた長崎大水害により流失したり、立て直されたりして今に至るこのアーチ橋郡は風情いっぱいです。

〈袋橋〉

〈東新橋〉

〈常磐橋〉

〈芊原橋〉
眼鏡橋の撮影ポイントしてもピッタリの魚市橋、袋橋。小説や映画にもなった「ぶらぶら節」の一節にもある大井手橋など、実にたくさんの石橋があります。
さらに中島川は、長崎港までに続くルートに、浜町に近い鐡橋や中央橋、2017年に約130年ぶりに開通された出島表門橋など、橋好き・橋マニアならずとも楽しめる橋スポットがたくさん!
それぞれの歴史を紐解きながら、写真に収めたりレポートにまとめたりするのも、きっといい思い出になるはずです。
AD注目の実力店や伝統の味を守り続ける老舗店など、全900軒が掲載!長崎の新店・定番店など美味しいお店が勢揃い。県内全域を網羅したグルメガイド本、書店にて絶賛発売中!
セメントなどは使っていない!石造りアーチ橋の高度な技術!
400年以上前に造られた、この眼鏡橋。当然、当時はセメントなどはありません。実は、地元の石を切り出して加工して、それを積んだ造り。石橋は石同士が競り合う力で保っているんです。

下から順に石を積み上げて、最後に要石(かなめいし)と呼ばれる石をアーチの真ん中にはめ込みます。これがピッタリとハマってしまえば、それぞれの石の重さが隣の石へとかかって、安定して崩れることがないのだそう。
この技術で、長らく眼鏡橋は保たれてきました。長崎大水害の際も一部の損壊で済んだのも、こうした古くからの高い技術によるものでしょう。
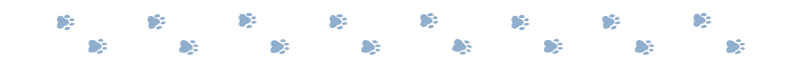

石橋群は中島川の上流まで、十数基にわたって続いています。川沿いに辿ってみるのもよいのではないでしょうか。
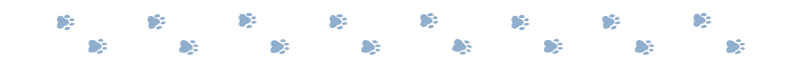
| 名称 | 眼鏡橋 |
|---|---|
| アクセス | 【JR長崎駅から】路面電車3号系統「蛍茶屋 行き」に乗車→「市民会館」電停下車→徒歩4分 【大浦天主堂・中華街方面から】路面電車4号系統・5号系統「蛍茶屋 行き」に乗車→「眼鏡橋」電停下車→徒歩3分 |
| 駐車場 | 周辺にコインパーキングあり |
| 備考 | 国指定重要文化財(指定年月日 昭和35年2月9日) |
| 場所 | 長崎県長崎市 魚の町・栄町と諏訪町・古川町の間 |
眼鏡橋の他のお話はこちら
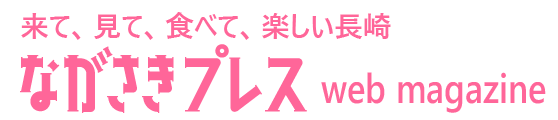
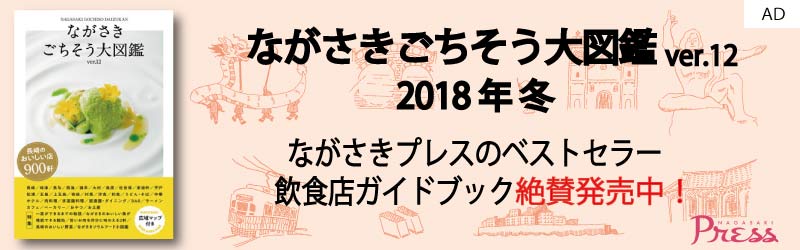


コメントを投稿するにはログインしてください。