![]() 「中島川石橋群」のおはなしvol.3
「中島川石橋群」のおはなしvol.3
今回は観光気分にハシ休め! 中島川石橋群 橋解説その②

前回は、中島川のメジャーどころ・眼鏡橋周辺の橋をご紹介しましたが、さらに上に進んでいきましょう!
まだまだ町家づくりや職人町が続くエリアです。当時の暮らしに想いを馳せながら、ぜひ橋を渡ってみてください。
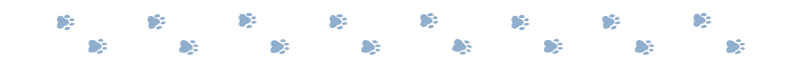
イモ?いえ、ススキです!芊原橋

自動車も通行でき、交通量も多い芊原橋(すすきはらばし)です。「芋(イモ)」ではありません。「芊(ススキ)」なんです。お間違えなきよう……。
名前の由来は、橋の周辺に草が生い茂っていた=芊々(せんせん)としていた、ということですが、なんだ!結局イモっぽい(失礼)!

以前は中紺屋町と今紺屋町をつなぐ橋として、中紺屋町橋、今紺屋町橋とも呼ばれていたそうです。
こちらも自動車が多く通行する場所なので、渡る際はお気を付けて。
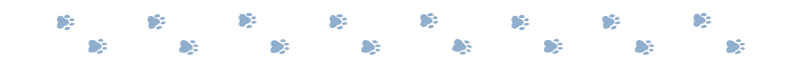
光永寺とセットで“一覧”すべし! 一覧橋

一覧橋は、中国福建省出身の豪商で、唐通事(中国語の通訳)を務めていたいう高一覧が明暦3(1657)年に架設した橋です。
以前は町名由来で桶屋町橋とも呼ばれていたのだとか。

高一覧は、この上流にある大井手橋も手掛けているということで、この付近への貢献度がうかがい知れますね。
一覧橋のたもとには光永寺が建っています。
この光永寺は、かつてあの福沢諭吉が一時寄宿し蘭学を学んだ場所でもあるのだとか。橋と共にチェックしてみて。
さらに、夜はライトアップされているので、こちらも見どころです。
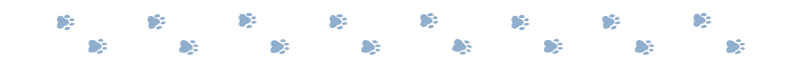
鳥も集い・渡る、歴史深い橋 古町橋

古町と麴屋町を結ぶ古町橋。
元禄10(1697)年に貿易商・河村嘉兵衛とその母・妙了尼の寄進によって架設されました。
この橋も享保6 (1721)年の洪水にはじまり、昭和57(1982)年の長崎大水害まで、幾度も崩壊や破損を繰り替えてきた歴史があります。
野鳥観測もできる良スポットなのだとか。

古町橋は、大水害後に架設しなおされた橋で、一覧橋、編笠橋、東新橋を合わせた4つの橋は昭和の石橋とも呼ばれています。
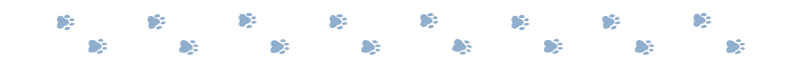
渡る人の人間味もあふれる“編笠”エピソード 編笠橋

今博多町と八幡町をつなぐ編笠橋。
その昔今博多町が「あめがた町」と呼ばれていたことから、転じて「編笠橋」という通もありますが、もうひとつ面白い由来が。
かつてこの付近には遊郭があり、この橋を渡る人たちは恥ずかしがって編笠で顔を隠していた、というエピソード。
諸説あるのが歴史の面白いところでもあると思いますが、人間味があふれていて、なんだかこちらを推したくなります。


橋のたもとには、小さな稲荷大明神が鎮座しています。
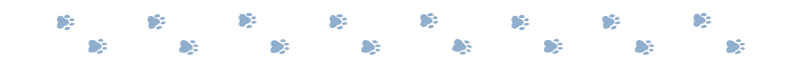
以上、合わせて8橋分の“長崎の橋”をご紹介しました。
でも、まだまだたくさんの橋があります。
折を見てまたご紹介していきますので、お楽しみに。
見て、渡って、撮影して。それぞれに橋を楽しんでみてください!
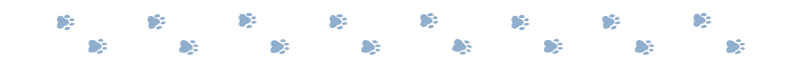
| 名称 | 中島川 |
|---|---|
| 駐車場 | 周辺にコインパーキングあり |
| 場所 | 長崎県長崎市 中島川 |
中島川石橋群の他のお話はこちら
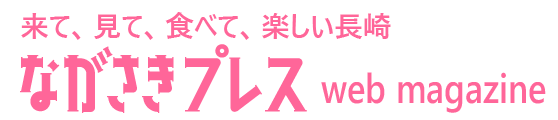


コメントを投稿するにはログインしてください。